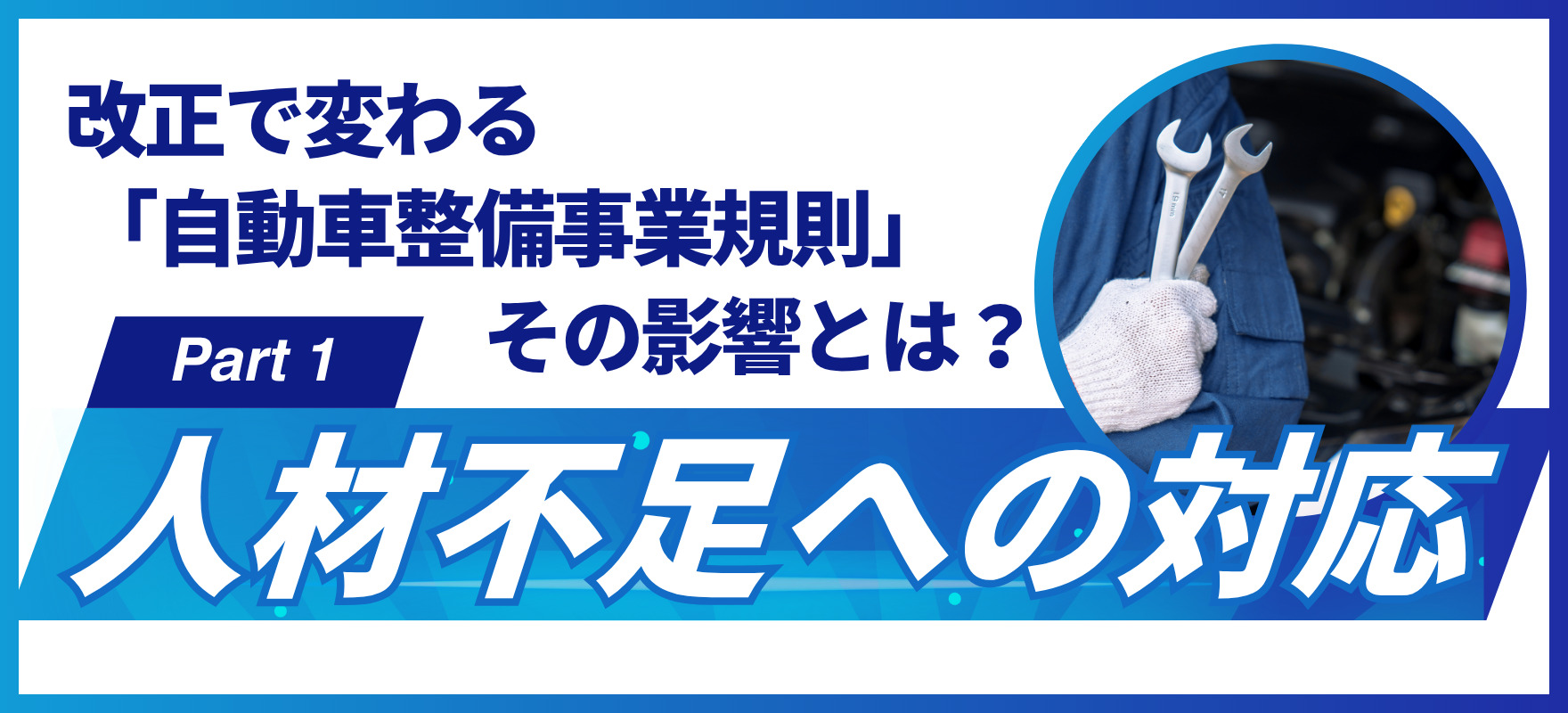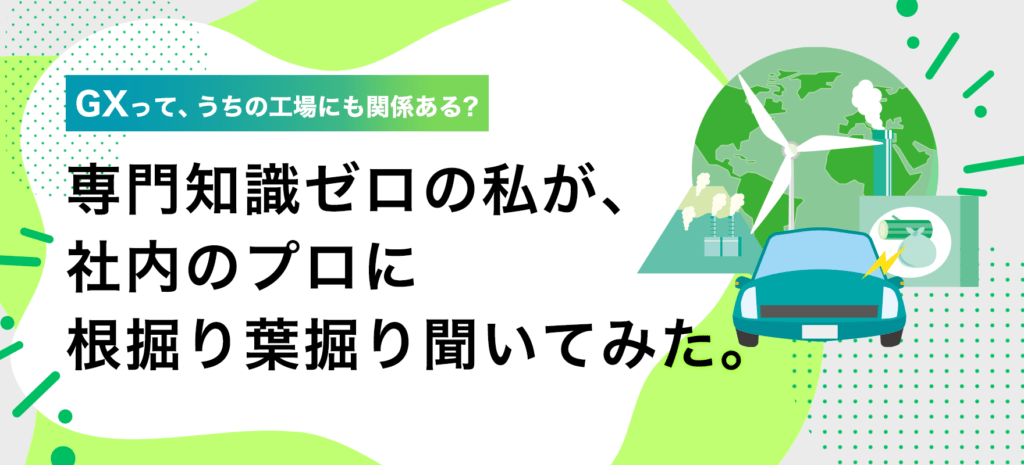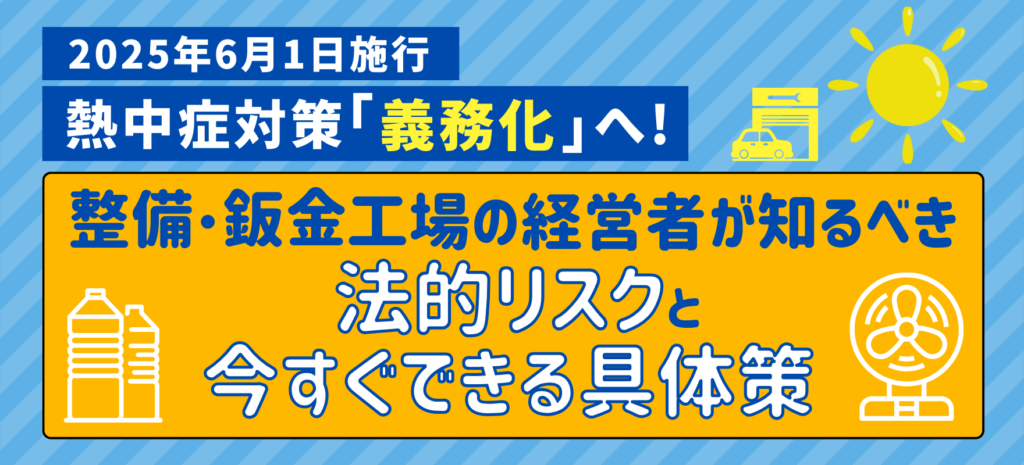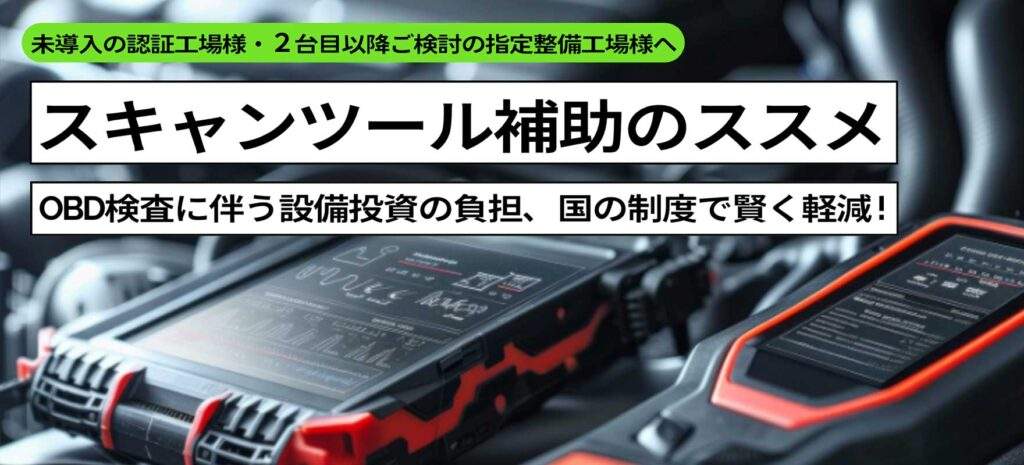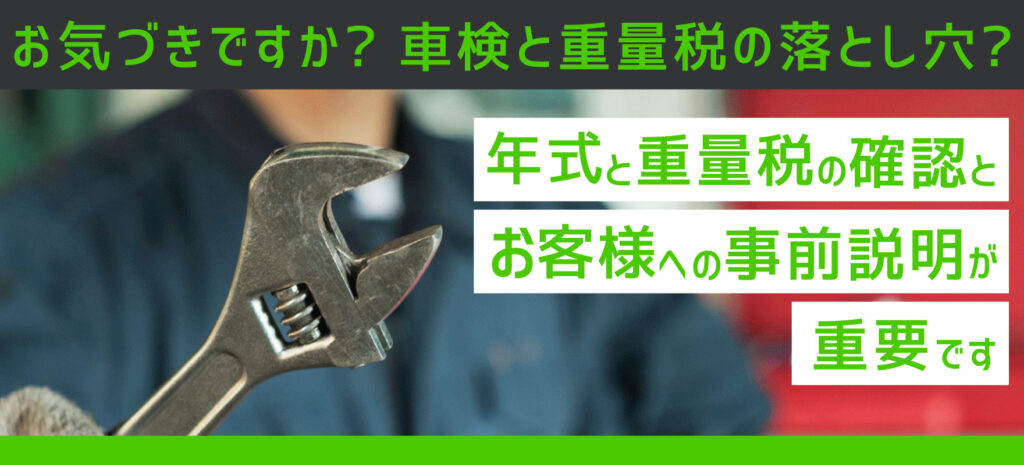改正で変わる自動車整備事業規則、その影響とは? 【パート1:人材不足への対応】
目次
国土交通省は自動車整備事業が直面する「技術の高度化」と「担い手不足」という二つの課題に対応するため、自動車整備事業規則の見直しを行い、2025年7月8日に、公布・一部施行しました。
この見直しは、整備現場の人材不足を補い、生産性を向上させ、新しい技術に対応することを目指したもので、主に規則を緩和する方向で進められました。整備人材確保・生産性向上・技術高度化対応の3点を目的に基本的に緩和という方向で見直されました。
パート1では、「整備人材不足」というテーマで、3つの主な変更点について、ご紹介します。
その1:「攻めの投資」が必要人員数の緩和の鍵に!
車検ラインを自社で保有する指定工場では、これまで事業規模に応じて配置すべき最低工員数が定められていました。しかし、近年、作業を効率化する新しい設備の普及が進む一方で、深刻な人手不足からこの基準を満たすことが難しくなり、やむなく指定工場の資格返上するケースもでてきます。
条件付きで規制緩和へ
このような状況を踏まえ、特定の条件を満たす指定工場(大型)において、以下の4つの条件を満たす場合、「5人」から「4人」へと緩和されることになりました。
【要チェック】行員数緩和の前提条件
- 省力化に資する設備・機器が導入されていること
- 合理的な業務管理体制が適切に確保されていること
- 工員の労働環境や処遇が確保されていること
- 工員の技術レベル(質)が適切に確保されていること
なお、今後は中型・小型・二輪の指定工場(現行4名)についても、同様の見直しが検討される見込みです。
この規制緩和は、人材確保に悩む事業者様にとって大きなチャンスです。指定工場の維持がしやすいという直接的なメリットだけでなく、その先にあります。緩和の条件を満たすために省力化設備導入や管理体制を見直すことが、事業所の生産性を向上させるきっかけになります。人手不足というピンチを、事業の質を高めるチャンスに変えてみませんか?
その2:未来への投資!「1級整備士」の市場価値が急上昇する理由
最終的な検査を担う「自動車検査員」の要件が、技術の進化に合わせて大きく変わります。その背景には、これから普及が加速する自動運転車の存在があります。無数の高度な電子制御装置の集合体であるこれらの車の安全性を正確に判断するには、複雑な電子システムを深く理解した専門性が不可欠となり、未来の自動車社会で事業を継続していくための重要な変更点となるでしょう。
知らないでは済まされない「新ルール」
この技術の高度化に対応するため、自動運転レベル3以上の車両の検査を行う自動車検査員には、現在の要件に加えて、「1級自動車整備士」の資格が必須となります。この新しい規則は、令和11(2029)年4月1日から施行されます。これにより、1級自動車整備士という資格が持つ価値と専門性が、これまでとは比較にならないほど高まると考えられます。
この新ルールは、事業者にとっては「1級整備士をどう確保するか」という課題を、整備士にとっては「自らの価値が上がる」という機会をもたらします。今後、高い専門性を持つ人材の重要性はますます高まることが予想され、計画的に人材を確保していく視点が求められるかもしれません。
その3: 若手や中途採用の成長を加速!整備士資格の実務経験を大幅短縮!
自動車整備業界が抱える「なり手不足」という課題に対し、若手人材の育成方法に影響を与える、注目すべきルール変更が実施されます。その背景には、近年の自動車整備が物理的な部品交換から診断機を駆使した電子制御の解析へとシフトしていることがあります。この変化に伴い、長年の経験則だけでなく、体系化された知識を持つ人材がより早い段階から現場で活躍することへの期待が高まっており、今回の変更は若手整備士のキャリア形成を後押しすることが期待されています。
若手のキャリアを後押しする、実務経験の短縮
この状況を受け、若手がよりスムーズにプロの整備士へと成長できるよう、資格取得に必要とされる実務経験の期間が短縮されることになりました。
具体的には、プロへの道のりが以下の通り短縮されます。
- 2級自動車整備士 : 3年 → 2年
- 3級自動車整備士 : 1年 → 6ヶ月
- 特殊自動車整備士: 2年 → 1年4ヶ月
実務経験短縮により、未経験で入社した人材も、早い段階で国家資格という明確な目標を達成できるようになります。この変化を、若手の成長と事業の発展を両立させる良い機会と捉え、新しい人材育成を検討してみてはいかがでしょうか。
その4: 学びのスタイルに革新!研修・講習のオンライン化がスタート
これまで、整備主任者研修や自動車検査員研修、そして自動車整備士養成施設における講習は、法令により原則として対面での実施が義務付けられていました。
今回のルール変更により、これらの研修・講習のうち、専門知識を学ぶ「座学」の部分についてはオンラインでの実施が可能になります。注意する点として、実践的なスキルを習得するための「実技講習」は、引き続き対面で行われます。これにより、場所や時間の制約が少なくなり、より多くの整備士が効率的に知識をアップデートできるようになることが期待されます。
最後に
一連のルール変更は、単なる規制緩和ではなく、見方を変えれば、国からの「未来の事業リスクとその対策」についてのメッセージと読み取れます。つまり、「人員配置や若手育成については柔軟に対応できる環境を整えるので、今のうちに必ず、未来の自動運転技術に対応できる準備をしておいてください」というサインです。私たちはこのサインをどう受け取り、備えるかが、今後の鍵となると考えられそうです。
パート2では、生産性向上・技術高度化への対応について紹介します。続けてご覧ください。
参考
国土交通省・報道発表サイト
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000341.html
国土交通省・報道発表資料PDF
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001899720.pdf
国土交通省・(参考)各アップデートの解説
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001899721.pdf
※この記事は2025年9月時点の情報です。できる限り正確な内容を心がけていますが、情報が変更されている可能性もございます。どうぞご留意ください。