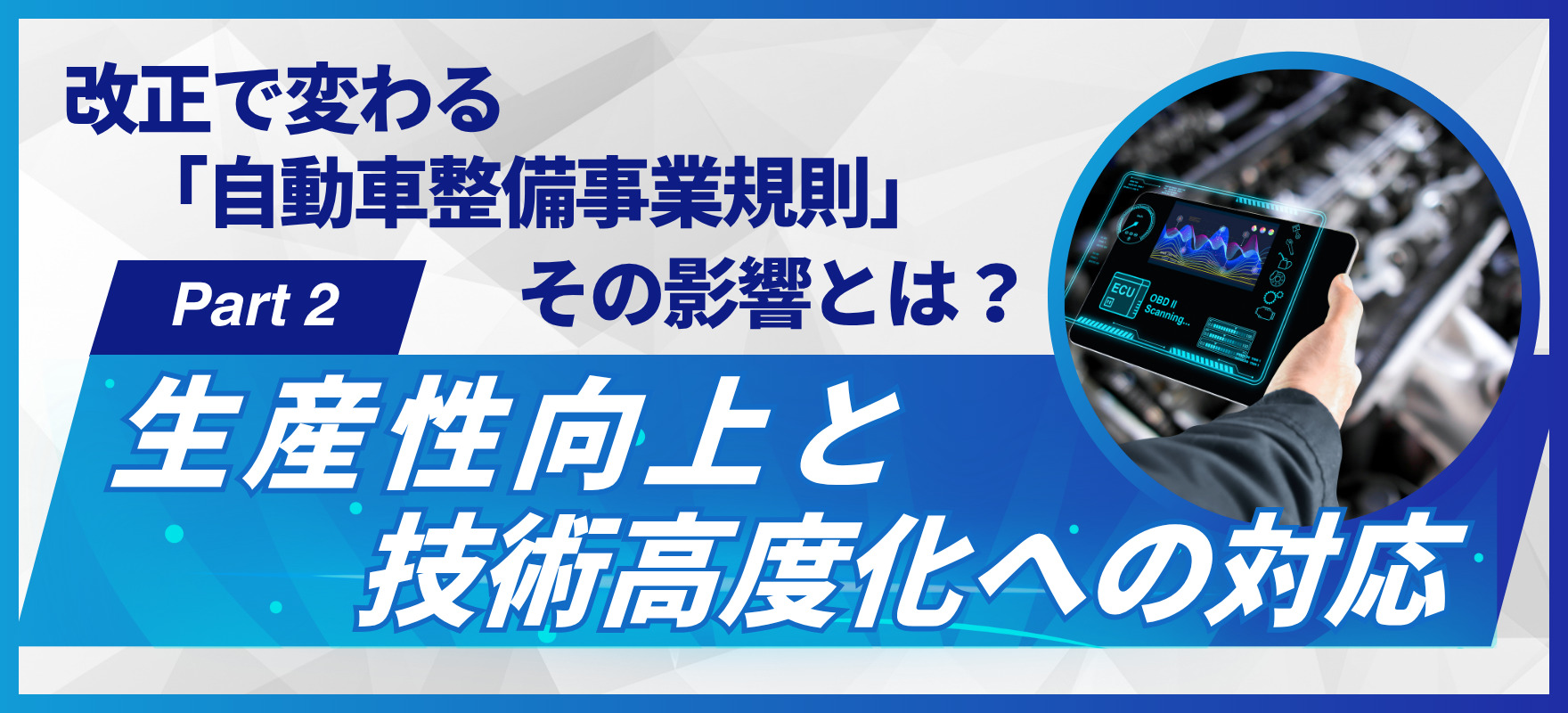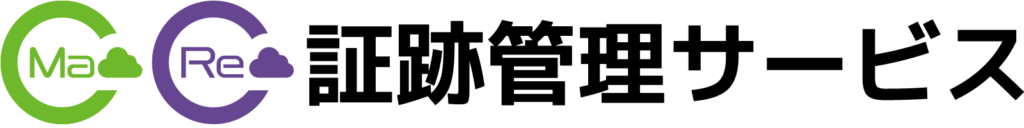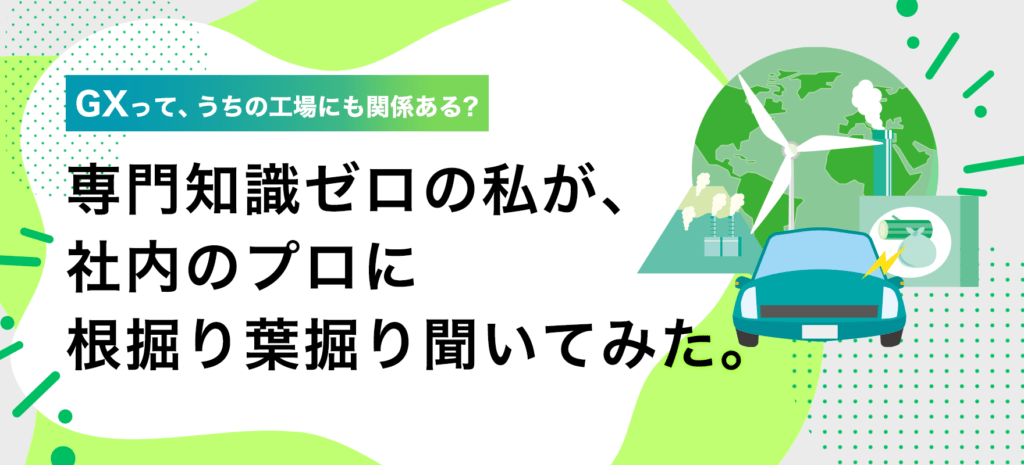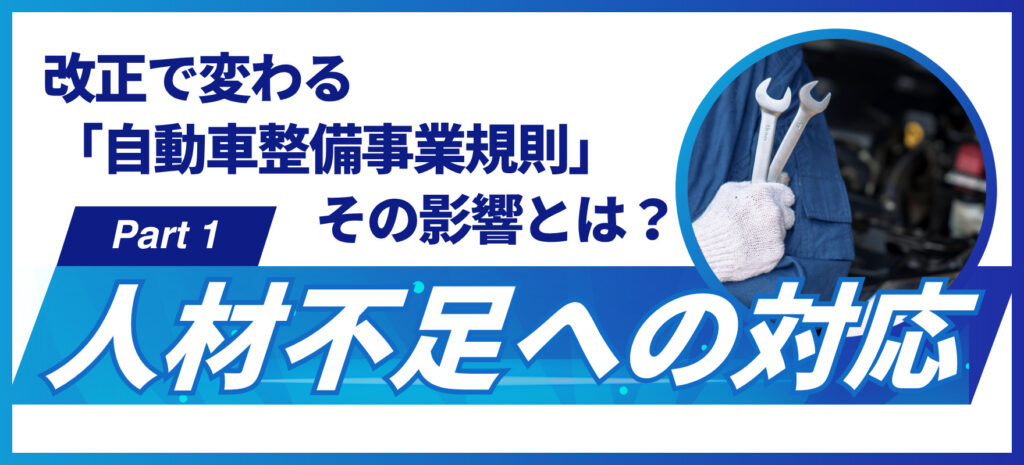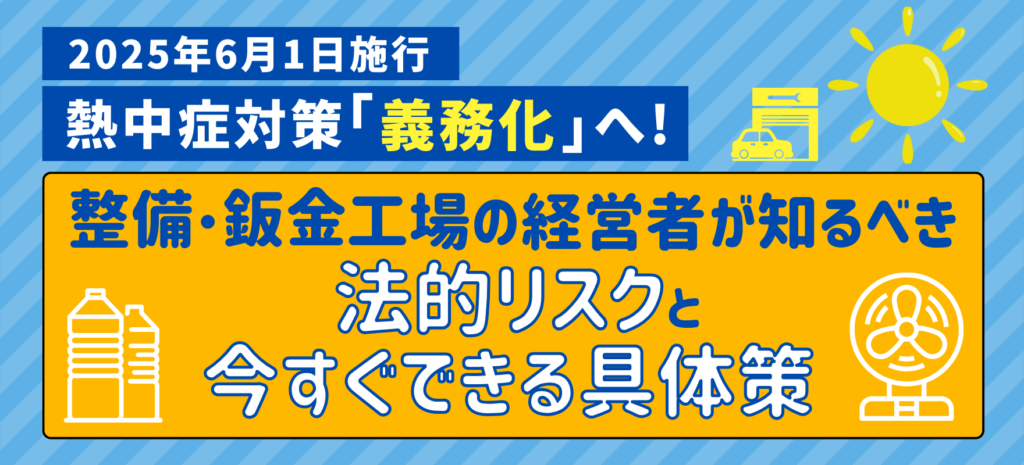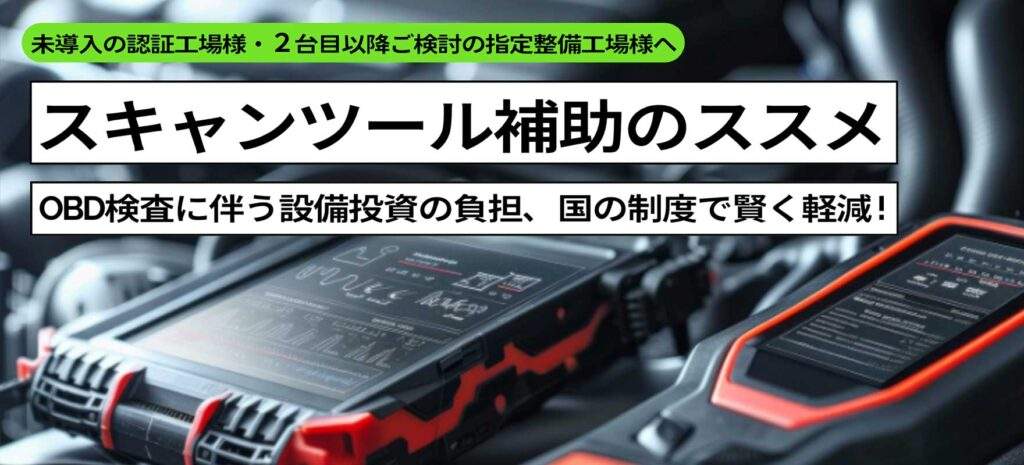改正で変わる自動車整備事業規則、その影響とは? 【パート2:生産性向上・技術高度化への対応】
目次
国土交通省は自動車整備事業が直面する「技術の高度化」と「担い手不足」という二つの課題に対応するため、自動車整備事業規則の見直しを行い、2025年7月8日に、公布・一部施行しました。
この見直しは、整備現場の人材不足を補い、生産性を向上させ、新しい技術に対応することを目指したもので、主に規則を緩和する方向で進められました。整備人材確保・生産性向上・技術高度化対応の3点を目的に基本的に緩和という方向で見直されました。
パート1では、「整備人材不足」というテーマで、3つの主な変更点について、ご紹介しました。今回はパート2として、「生産性向上」と「技術の高度化への対応」というテーマで4つの主な変更点について、ご紹介します。
その1:コスト削減にも?認証工場の設備基準、見直しのポイント
これまで認証工場が備えるべき機器は法律で定められていましたが、技術の進化により、あまり使われなくなった機器と、逆に新たに必要となる機器が出てきました。今回の見直しでは、この現状に合わせて設置義務が変更されます。
これらの機器は、設置義務がなくなります
今回の見直しで、以下の機器については設置義務が廃止されます。これにより、旧式な機器の維持や更新にかかっていたコストを削減できる可能性があります。
【廃止される主な機器】
- タイヤの傾きを計測する機器
- 普通(大型)・普通(中型)・大特を扱う工場を除き、小型車・軽・二輪の整備に使用しない機器
- バッテリテスタがあれば比重計
- 整備用スキャンツールがあれば、エンジンタコテスタ・タイミングライト
【追加される機器】
- 認証の新規取得時や事業移転時から整備用スキャンツールの設置が義務化されます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001899721.pdf
【要注意】「スキャンツール」は必須装備へ
一方で、これからの整備に不可欠な機器として、「整備用スキャンツール」の設置が新たに義務化されます。この義務化は、認証を新規で取得する時、または工場を移転する時から適用されます。現代の電子制御された自動車を正確に診断・整備するためには、スキャンツールが不可欠であるという国からの明確なメッセージと言えるでしょう。
この見直しは、不要な機器の維持費の削減できるというメリットと、スキャンツールへの投資が必須になるという義務があります。この見直しを自社の設備全体を見直す好機と捉えてみてはどうでしょうか。例えば、補助金制度などを積極的に活用し、計画的にスキャンツールを導入するなど、他の省力化機器や最新システムへの投資をおこなうことで、単なるコスト削減に留まらず、事業所全体の生産性向上ができるのではないでしょうか。
その2: 業務効率アップ?点検記録簿「電子化」解禁!
これまで自動車ユーザーは、紙の「点検整備記録簿」を車内に備え付ける義務がありました。整備事業者側でデータを電子管理していても、別途紙で交付する必要があり、二重管理の手間が発生していたのです。今回の見直しでは、この現状に合わせて記録簿の保存方法が変更されます。
点検記録簿、これからはデータでOKに
今回の改正により、「点検整備記録簿」を電子データで保存・提示することが正式に認められます。これにより、非効率な二重管理から解放され、ペーパーレス化による業務効率化が期待できます。(紙での保存も引き続き可能です)
【認められる保存方法の例】
- スマートフォンやタブレット内のファイル
- SDカードなどの外部メディアへの保存
- 紙の記録簿をスキャンしたPDFファイルなど
【要注意】「いつでも見せられる」ことが絶対条件
一方で、この電子化には厳格なルールが伴います。当局から提示を求められた際、「直ちに」「わかりやすい状態で」表示できなければなりません。
スマートフォンの故障、バッテリー切れ、電波不良などで表示できない場合は、要件を満たさないと判断されます。そのため、いつでも確実に見せられる運用方法やシステムの確立が不可欠という、国からの明確なメッセージと言えるでしょう。 この見直しは、ペーパーレス化による業務効率化というメリットが生まれる一方、「いつでも提示できる」準備が必要という義務があります。
例えば、 点検記録簿だけでなく、見積書や請求書なども含めた一連の書類を電子化するシステムを導入するなど、業務フロー全体を改善することで、単なるペーパーレス化に留まらず、顧客満足度の向上と事業所全体の生産性向上ができるのではないでしょうか。
その3: 点検作業の「当たり前」が変わる。スキャンツールの活用が新基準へ
従来の車両点検は、整備士の目視や操作による確認が中心でした。しかし、近年の自己診断機能を搭載した自動車では、スキャンツールを用いることで、より客観的で精度の高い点検が可能です。今回の見直しでは、この実情に合わせて点検方法が変更されます。
【対象項目】スキャンツールで確認できる5つのポイント
今回の改正により、これまで目視等が基本だった5つの点検項目について、スキャンツール等を活用した確認方法が正式に認められます。これにより、作業時間の短縮と診断精度の向上が期待できます。
- 【日常点検】
- ① ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキのきき
- 【定期点検】
- ② ブレーキ・ペダルを踏み込んだときの床板とのすき間
- ③ 倍力装置(ブレーキ・ブースター)の機能
- ④ 二次空気供給装置の機能
- ⑤ 排気ガス再循環装置の機能
この見直しは、事業者にとって、作業時間の短縮や診断精度の向上という直接的なメリットをもたらします。作業時間短縮によって、より付加価値の高い業務を行うことや、お客様への丁寧な説明への時間を行うなど、人でなければできないサービスの質の向上に取り組めるのではないでしょうか。
まとめ
今回の見直しは、整備業界における「デジタル化」の流れをより一層明確にするものと言えそうです。この大きな流れに対応するためには、部分的な変更に留まらず、事業所全体の「業務フローを見直す」という視点が今後大切になるかもしれません。
導入する設備、書類の扱い方、そして点検の進め方が変わる今、デジタルツールによる効率化と、人でなければできない付加価値のあるサービスを両立させる。そうした取り組みこそが、企業の生産性を向上させる鍵となるのではないでしょうか。
参考
国土交通省・報道発表サイト
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000341.html
国土交通省・報道発表資料PDF
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001899720.pdf
国土交通省・(参考)各アップデートの解説
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001899721.pdf
※この記事は2025年9月時点の情報です。できる限り正確な内容を心がけていますが、情報が変更されている可能性もございます。どうぞご留意ください。