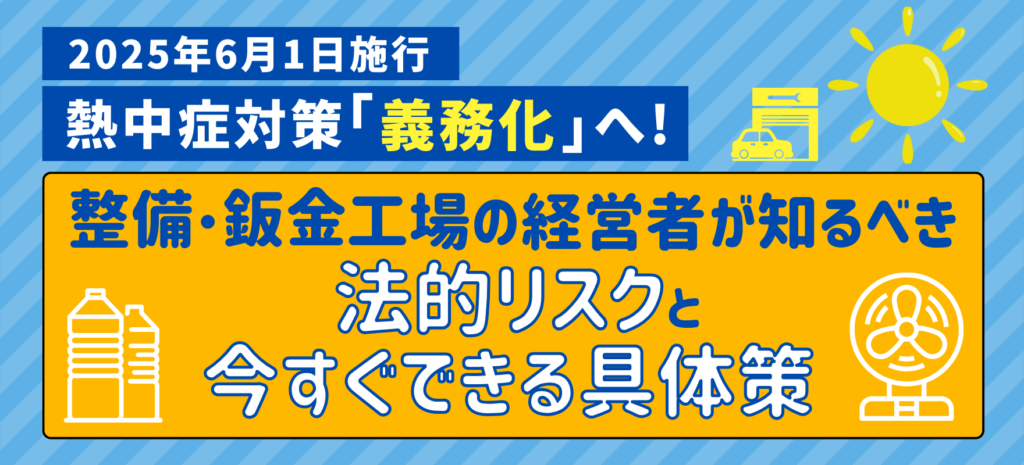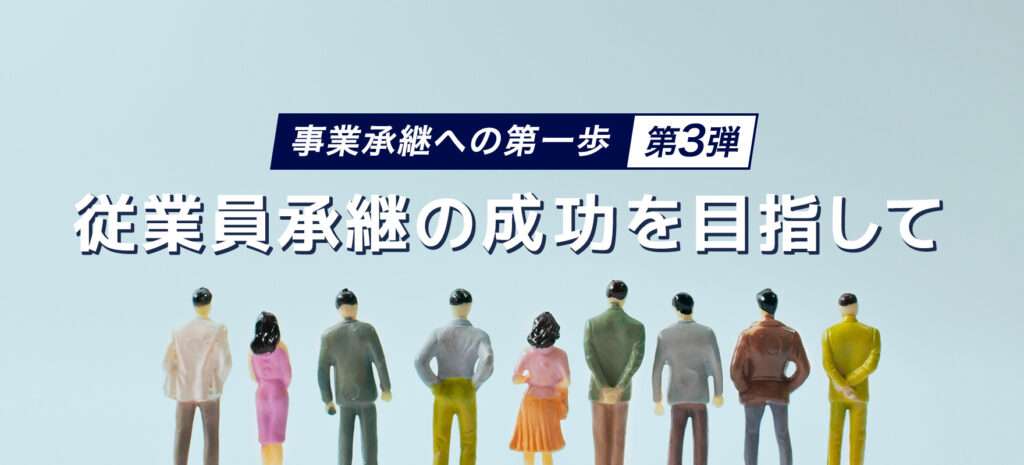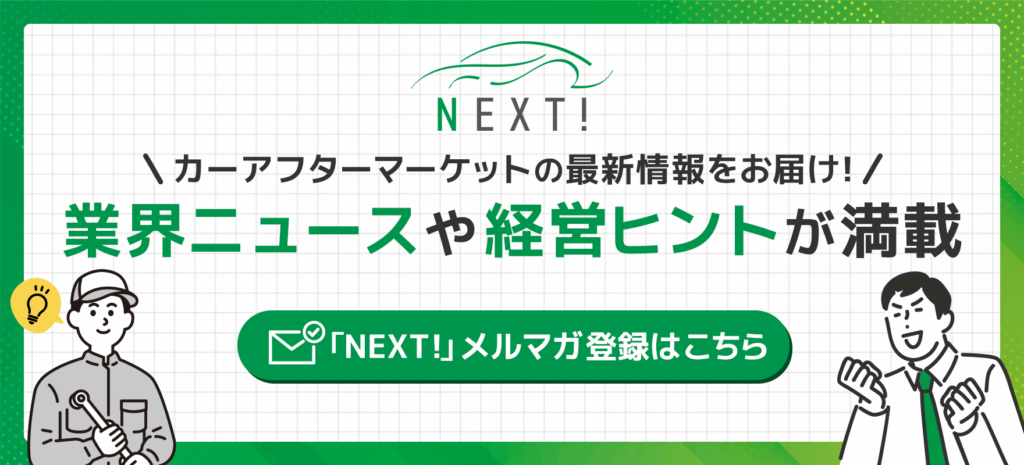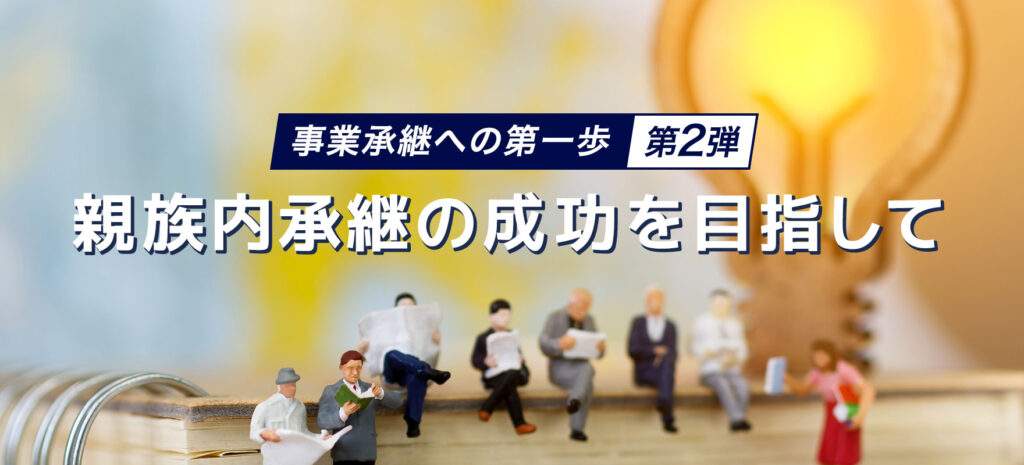車体整備業の未来を拓く「事後検証性」の確保とは ~ 業界課題と新指針・ガイドラインを読み解き、事業成長へ繋げる ~
目次
【記事監修】株式会社ブロードリーフ 高田 芳弘
序章:車体整備業界が直面する構造的課題
日々、お客様のカーライフを支えるため、真摯に業務に取り組む車体整備事業者の皆様。しかし、その丁寧な仕事に見合うだけの対価を、果たして得られているでしょうか。
現在の車体整備業界は、深刻な構造的課題に直面しています。
- 人材不足とコストの増大
少子高齢化による人材不足に加え、物価上昇が経営を圧迫。利益を確保できなければ、従業員の待遇改善もままならず、さらなる人材流出を招くという悪循環に陥っています。 - 自動車技術の高度化への対応
自動ブレーキや運転支援システム(ADAS)の普及により、車の構造は複雑化の一途をたどっています。修理・整備には高価な設備投資や、常に新しい知識を習得し続けるための教育コストが不可欠となりました。 - 適正な価格転嫁の困難さ
これらのコスト増を修理価格へ適切に転嫁できている事業者は、決して多くありません 。事実、内閣官房や公正取引委員会などが公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において、車体整備業界は「労務費の転嫁率ワースト1位」という不名誉な認定を受けています。
こうした状況が続けば、事業者の廃業が進み、結果として「車の安心・安全」を支える社会基盤そのものが揺らぎかねません。この危機感から、国土交通省だけでなく、内閣府、公正取引委員会、中小企業庁といった関係省庁も一体となり、業界の健全化に向けた大きな改革に乗り出しました。
その改革の核となるのが、近年立て続けに公表された複数の「指針」と「ガイドライン」です。これらは、これからの車体整備業界の進むべき道を示す『地図』と『コンパス』とも言えるでしょう。
第1章【国の動きと文書の全体像】
国の改革の柱となるのが、複数の「指針」と「ガイドライン」です。これらが策定された背景と関係性を理解することで、進むべき道が明確になります。
策定の経緯:大手中古車販売会社の保険金不正請求問題で前後した「指針」と「ガイドライン」
本来、指針とガイドラインは補完関係にあり、従来は方向性を示す指針が提示され、その上で具体的な実行手段としてガイドラインが策定されるのが一般的でした。
しかし、2023年に発覚した大手中古車販売会社による保険金の不正請求問題を受け、社会全体で消費者保護への意識が急速に高まりました。この事態を重く見た国土交通省は、急遽「消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン」を先行して策定・公表するに至ったのです。
この経緯により、指針とガイドラインの公表順序は結果的に前後しましたが、「指針」が目指す適正な価格交渉を実現するためには、その大前提として「ガイドライン」が求める仕事の透明性確保が不可欠である、という構造に変わりはありません。
各指針・ガイドラインの概要
ここで、それぞれの文書が持つ役割を改めて整理します。
【指針①】車体整備事業者による適切な価格交渉のための指針
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001867762.pdf
- 発行元:国土交通省(2025年3月4日)
- 概要:労務費や原材料費の上昇を適切に価格転嫁できていない車体整備業界に向け、自社の責任に基づく見積作成や、人件費等の上昇を考慮した工賃単価の提案、損害保険会社との交渉における留意点など、事業者が取り組むべき事項をまとめたものです。
【ガイドライン①】修理工賃単価に関する対話・協議のあり方にかかるガイドライン
https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/syuri_guideline.pdf
- 発行元:一般社団法人日本損害保険協会(2025年2月17日)
- 概要:金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」や協会の「損害保険の保険金支払に関するガイドライン」において、車体整備事業者に対する保険金(賠償金)の直接支払にあ たり必要な態勢整備を求めていることを受け、会員会社による取り組みの考え方をまとめたものです。
【ガイドライン②】車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001734259.pdf
- 発行元:国土交通省(2024年3月29日)
- 概要:事故車両をはじめとする車体の板金や塗装などの整備作業について、自動車ユーザーである消費者に対し車体整備の透明性を十分に確保するため、車体整備事業者において実施することが求められる取組みや実施することが望ましい取組みをガイドラインとして示すものである。
これら3つの文書は、相互に関連していますが、中でも事業者がまず押さえておくべきなのが、「【指針①】整備事業者による適切な価格交渉のための指針」と「【ガイドライン②】車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン」です。ここでは、この2つの要点を掘り下げて見ていきましょう。
第2章【適正な価格交渉を実現する「指針」について】
(指針①「車体整備事業者による適切な価格交渉のための指針」)
ガイドラインが主に「消費者保護」に焦点を当てているのに対し、国土交通省が公表した「車体整備事業者による事故車修理の適切な価格交渉の促進のための施策(指針)」は、車体整備事業者と損害保険会社との間の公正な取引関係の構築を目指すものです。
本指針は、車体整備における商慣行に留意しつつ、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房、公正取引委員会)の趣旨を踏まえ、自動車ユーザーや損害保険会社に対して適切な価格交渉がなされるよう、車体整備事業者が取り組むべき事項を取りまとめたものです。
具体的には、自社の責任による見積作成や、人件費等の上昇を根拠とした価格交渉、標準様式の活用などが推奨されています。
なぜ今、透明性をもって損害保険会社に説明することが重要なのか
車体整備では板金塗装等の高度な技能とフレーム修正機や塗装ブース等の大規模設備投資が必要で、車体整備事業者はこれらを考慮した適切な技術料設定が求められる。作業内容・工程は修理後の外観からは容易に確認できないため、損害保険会社及び依頼者に対して修理内容と価格項目について透明性をもって説明し納得感を得る必要がある。
労務費の転嫁を含む適切な価格設定や請求においては、車体整備事業者が自社の責任と考えに基づき透明性をもって損害保険会社に説明できることが重要である。修理の透明性確保と適正な技術料設定により、業界の信頼性向上が図られる。事業者の主体的な説明責任が適切な価格設定の基盤となります。
指針が示す9つの具体的な取り組み
指針には、自社の技術や仕事の価値を正当に主張し、適正な利益を確保するための9つの取り組みが示されています。
保険修理における価格交渉の9つのポイント
1. 自社の責任と考えによる見積りの作成
保険会社任せにせず、自らが持つ専門知識と経験に基づき、責任を持って見積りを作成することが大前提であると示されています。必要な作業を専門家として判断し、主体的に見積りを提示することが、公正な価格交渉の第一歩となります。
2. 人件費等の上昇も考慮した工賃単価の提案
消費者物価指数だけでなく、従業員の賃金上昇や光熱費、設備投資など、自社の費用構造を正確に分析することが重要です。その分析に基づき、実態に合った工賃単価を算出し、価格転嫁を提案することが求められます。
3. 標準的な作業時間と実態を踏まえた価格請求
「自研指数」などの標準的な作業時間を基準としつつも、車両の損傷が激しい場合や、付随作業で指数以上の時間がかかった場合は、その理由を丁寧に説明し、特殊事情がある場合は、個別交渉することが重要です。
4. 「見積書・領収書」「作業記録簿等」の標準様式の使用
作業内容及び価格項目の透明性を高めるため、指針で掲げる「見積書・領収書」「作業記録簿」の標準様式も参考にし作業内容に応じた請求を行うこと。複数の項目を一つにまとめたり、「総額値引き」といった曖昧な表記は避け、無料とする作業であっても「0円」と記載してすべての作業履歴を残すべきです。
5. 損害賠償における代車費用の支払いに関する考え方の理解
代車費用が保険でどのように支払われるか(過失割合など)を正しく理解し、必要に応じて依頼者(カーオーナー)に確認してもらうことが重要です 。対物賠償保険の支払いの考え方を理解することが大切です。
6. 透明性・公平性が疑われないような請求・説明
合理的な理由なく、保険修理による修理とそれ以外の修理で価格に差をつけたり、交渉による減額を見込んで初期の価格設定を不当に高い価格を提示したりすべきではありません。常に価格の透明性と公平性を意識した請求と説明が求められます。
7. 損害保険会社との交渉における留意点
修理方法などで損害保険会社と見解が異なる場合は、なぜその方法を採用するのか、専門家として丁寧に理由を説明しましょう。逆に、相手方の見解に疑問があれば、その根拠について説明を求め双方が建設的に対話することが大切です。
8. 協定に時間を要する場合の対応
1週間を超えて見解が相違する場合は、依頼者に状況を説明する必要があります 。交渉が長引くことによるデメリット(代車費用が増えるなど)も伝え、依頼者の意向を確認しながら対応を進めます。
9. 依頼者に対する適切な情報提供
実施した、あるいは実施する予定の修理内容について、依頼者から求められた場合は作業内容と見積を丁寧に説明を行うこと。また、保険修理は原則「現状復旧」であり、それを超える修理は差額を支払うことで可能になる、といった情報も適切に提供しましょう。
車体整備は、高度な技術と高額な設備投資が求められるため、事業者はそれに見合った「技術料」を適切に設定する必要があります。一方で、修理内容は外観から分かりにくいため、保険会社や顧客に対しては、価格と作業内容の透明性を確保し、納得のいく説明をすることが求められます。
これらの点を踏まえ、労務費などを適正に価格転嫁し請求するためには、事業者が自社の考えに責任を持ち、損害保険会社に透明性のある説明をできることが最も重要です。
国土交通省による対応
国土交通省は、関係業界団体の協力も得ながら車体整備事業者による車体整備事業者が取り組むべき事項の取組状況を確認するとともに、関係省庁(公正取引委員会、金融庁及び中小企業庁)と連携して車体整備事業者による価格交渉の実態・課題等を継続的に把握する。
第3章【「透明性確保に向けたガイドライン」の本質とは】
(【ガイドライン②】車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン)
ガイドラインの目的と効力
価格交渉の指針を実践する上で、その成否を分けるのが「透明性確保に向けたガイドライン」への対応です。このガイドラインが求める目的は、消費者に対し車体整備の透明性を十分に確保するため、車体整備事業者において実施することが求められる取組みや実施することが望ましい取組みをガイドラインとして示すものです。
そのポイントは「事後的な検証体制」を確保することと消費者にとって必要な情報が適切に提供される事にあります。
「事後検証性」とは、撮影された写真等から同等の見積もりが再現可能となるほどの制度で記録を行なうことを要求するものです。大手中古車販売会社の保険金不正請求問題では、過去の修理記録の多くが残っておらず、不正の有無を十分に検証できない事態となりました。この教訓から、作業プロセスの記録と保存が極めて重要視されるようになったのです。
このガイドラインは法的な強制力はないとされていますが、このガイドラインが持つ本来の目的について、国土交通省は次のように定めています。
このように、ガイドラインは罰則を伴うものではありませんが、国が業界に求める「あるべき姿」を示したものです。また、国土交通省は、このガイドラインを「指導・監督を行う際の指針の一つとする」と明言しており、事実上の業界標準となると言えるでしょう。
明確な証跡を残すことは、万一のトラブルから自社を守るだけでなく、損害保険会社との価格交渉において「客観的な根拠」として有力な材料となります 。
ガイドラインが求める5つの必須項目
①車体整備作業に係る画像情報の記録・保存
- 入庫時の記録
入庫直後、作業開始前の車両状態を撮影します。ナンバープレートを含めた全体写真が必要です。これにより、修理前の車両状態を明確に記録できます。 - 作業中の記録
修理箇所の作業実施中の状況を撮影します。交換部品も写真に残します。作業の透明性を確保し、後から確認できるようにします。 - 完了時の記録
作業実施後の完成状態を撮影します。写真には撮影時刻の記録が必要です。修理完了後の状態を明確に記録し、品質を証明します。
それぞれの工程で、車両を特定することができる情報(例:ナンバープレートを含めた画像)が必要です。これらの画像記録は、整備内容の透明性を確保し、消費者と整備事業者の双方を保護する重要な役割を果たします。
なお、写真撮影の方法について、損害保険協会から出されている「車体整備の消費者に対する 透明性確保に向けた取組みについて」という資料が参考になりますのでご紹介します。
参考:https://www.sonpo.or.jp/news/release/2024/240919_chirashi_2.pdf
②車体整備作業の内容・方法に係る情報の記録・保存
- 見積書段階
作業開始前の見積もり内容を詳細に記録します。これには修理箇所、使用部品、作業時間などの情報を含みます。見積もりは消費者との契約の基礎となります。 - 作業中の変更
作業中に発生した変更点を記録します。追加作業や部品交換の必要性が生じた場合は、その理由と内容を明確に記録し、消費者に説明します。 - 最終整備の内容
最終的な整備内容を受付票・車体整備記録簿に記載し、2年間保管します。実際に行った作業内容を正確に記録することで、後日の確認や検証が可能になります。 - 部品・材料情報
使用した部品や塗料の配合などの情報も記録します。純正部品か社外品か、新品か中古品かなどの情報も含め、使用材料の詳細を残します。
③車体整備の料金に係る情報の記録・保存
- 事前見積もり
最初の見積もり内容と金額を記録します。これは消費者との初期合意の基礎となるもので、作業内容と料金の詳細を明確に示す必要があります。 - 変更時の見積もり
作業内容に変更があった場合の見積もりを記録します。変更の理由と追加費用の内訳を明確にし、消費者の理解と同意を得ることが重要です。 - 最終請求書
最終的な請求内容と金額を記録します。実際に行った作業と使用した部品・材料に基づいた正確な請求書を作成し、保管します。 - サービス作業の記録
無料で行った作業であっても、その内容を「0円」と明記し、作業履歴をすべて残します。
④車体整備に係る情報の関連付け
記録した情報を確実に保管し、いつでも取り出せる体制を整えることが求められます。
具体的には、これまで記録してきた①画像、②作業内容、③料金の3つの情報を「電磁的記録(デジタルデータ)」で関連付けて保存し、少なくとも2年以上保存、いつでもすぐに確認できる状態にしておく必要があります。
- 画像情報
車両の入庫時、作業中、完了時の写真を保存します。これらの画像は整備内容の視覚的な証拠となり、作業の透明性を確保します。画像には撮影日時の情報も含めることが重要です。 - 整備内容
特定整備記録簿など、作業内容の詳細記録を保存します。使用部品、作業手順、技術者名など、整備に関する全ての情報を記録し、後日の確認ができるようにします。 - 料金情報
見積書や請求書などの料金関連書類を保存します。料金の内訳、変更履歴、最終請求額など、金銭に関わる全ての情報を透明に記録します。
⑤消費者への適切な説明と了承
- 整備内容の説明
必要な整備内容と理由を消費者に分かりやすく説明します。専門用語を避け、図や写真を用いて視覚的に理解しやすい説明を心がけましょう。 - 料金の説明
整備にかかる費用の内訳を明確に説明します。部品代、工賃、諸経費など、請求項目ごとの金額と理由を丁寧に説明することで消費者の理解を得ます。 - 変更時の説明
整備にかかる費用の内訳を明確に説明します。追加作業の必要性や予想外の部品交換など、変更の背景を誠実に伝えることが重要です。 - 了承の記録
消費者からの了承を書面で残します。説明内容と消費者の同意を記録することで、後日のトラブルを防止し、双方の安心につながります。
変革を乗り越えるー信頼を勝ち取るためのIT活用
ここまで見てきたように、自動車修理業界は大きな転換点を迎えています。お客様への説明責任を果たし、作業工程をすべて記録・保管し、保険会社と公正な交渉を行う。これらすべてを実践することは、業界全体の信頼回復のために不可欠です。
しかし、ここまでお読みいただき、「対応すべき項目が多すぎる」「現場の業務負担が増えてしまう」と感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に日々の業務に追われる中で、これらすべての記録・管理・情報提供を手作業で行うには、計り知れない負担となります。1案件につき50枚~60枚もの写真の整理、書類の作成、情報の保管が必要となり…その手間に忙殺され、本来集中すべきお客様へのサービスや技術向上に時間を割けなくなってしまっては本末転倒です。
この大きな変化の波を、乗り越える方法があります。
第4章【ガイドライン対応を勝ち抜くソリューション】
本指針ならびにガイドラインを受け、当社では『証跡管理サービス(仮称)』を企画・開発しています。本サービスは、国土交通省や損害保険協会が定める厳格な基準(指針及びガイドライン)に沿っています。車の修理業界において、修理工場、保険会社、そしてカーオーナーが安心して利用できる「業界標準」となるサービスを目指しています。
他社のサービスは、修理の過程や写真をカーオーナーに見せることに重点を置いていますが、当社のサービスは「修理が適切に行われたか後から確認できること(事後検証性)」を最も重視して設計されています。この「事後検証性の確保」がなければ、本当の意味での業界標準となるサービスとは言えない、というのが本サービスの基本的な考え方です。
主な特長
写真整理はもう不要!スマホ・タブレットで完結する画像管理
タブレットやスマホで作成した見積を呼び出し、その見積明細から修理箇所の写真を撮って保存できます。撮った写真をわざわざパソコンに取り込んで整理する手間がなくなるので、作業がぐっと楽になります。
修理画像撮影を完璧にサポート!
当社のシステムは、入庫から納車までの写真撮影を徹底サポート。撮り忘れてしまう心配はもうありません。入庫時の写真が自動でリストアップされたり、見積もり明細から「この工程の写真を撮ってください」と指示が出たりと、システムが撮影をナビゲートしてくれるため、お客様への透明性の高い情報提供を確実に行えます。
修理状況を見える化しお客様も納得の透明性!
修理の進捗状況をお客様、保険会社、元請事業者の皆様にリアルタイムで共有し、高い透明性を確保しています。具体的には、入庫から納車までの修理画像、関連する帳票、そして修理代金に関する情報をいつでもご確認いただけます。
クラウドで安心!承認依頼から履歴管理までシームレスに
見積もりや修理の画像を共有したら、お客様や保険会社等にそのまま承認を依頼できます。さらに、「いつ」「誰が」「どのような内容を」承認したかが時系列でしっかり記録されます。これらの情報はクラウドサービス上で高いセキュリティ精度で保管されるので、安心してご利用いただけます。
まとめ「変革を好機とし、信頼と事業成長を掴むために」
今回の指針・ガイドラインの策定は、一部の事業者にとっては業務負担の増加と感じられるかもしれません。しかし、これは業界の悪しき慣習を断ち切り、誠実な仕事を行う事業者が正当に評価される時代への転換点です。
自社の仕事のプロセスを可視化しオープンにすること(透明性確保)。それによって得られた顧客からの信頼を背景に、仕事の価値を正当に主張すること(価格交渉)。この両輪を回すことこそが、これからの車体整備事業者には求められています。
弊社は、この歴史的な転換期において、テクノロジーの力で事業者の皆様を全力で支援することをお約束します。煩雑なガイドライン対応を事業成長のチャンスに変えるパートナーとして、ぜひお声がけください。未来に向けた第一歩を、共に踏み出しましょう。
※本記事の内容は、2025年7月時点で公表されている情報や資料に基づき作成しております。掲載内容には細心の注意を払っておりますが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。重要な判断の際には、必ず関連省庁などが公表している原文をご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の経営判断や法的な助言を行うものではありません。本記事の情報を利用した結果として生じたいかなる事象についても、責任を負いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
監修者プロフィール
高田 芳弘(たかだ よしひろ)
株式会社ブロードリーフ 企画グループ
一般社団法人 日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連) 外部監事